昨日は、中曽根康弘元総理の内閣自民党合同葬が行われた日でした。他方で、皇室と多数の国民が崇敬する伊勢神宮の最大神事の神嘗祭が行われた日でもありました。もとより、後者は以前から、太古から続く重要な慶事であり、そのことは政府も常識で知る範疇のことであるというのが、権威ある思想行動団体の一水会が知らしめた判断であろうと思います。

さて、中曽根康弘元総理の内閣自民党葬に関して、羽生田光一文部科学大臣が指示して、国立の大学など、あるいは全国の教育委員会に、半旗(弔旗)の掲揚と、黙とうを求める通達を出し、その実施を求める指示・要請を行いました。途中から、羽生田大臣は、強制するものではない、その実施状況の情報収集をするわけではないと釈明していましたが、あまさに馬脚を現す。予算の配分を受ける教育機関が忖度をしないことの方が珍しいことと思います。さて、結果はどうであったでしょう。
私は、政治的な関心から、昨日はその実況を見め回るために、周辺の市立小中学校、都立高校、そして国立大学を巡りました。もとより、私が黙とうをしたということはありません。
自分が観察した範囲で、町田市立の小中学校で半旗(弔旗)の掲揚は無かった、それからして、教師や児童生徒の黙とうは行われなかっただろうと思います。東京都立の高校も同様に半旗(弔旗)の掲揚はありませんでした。


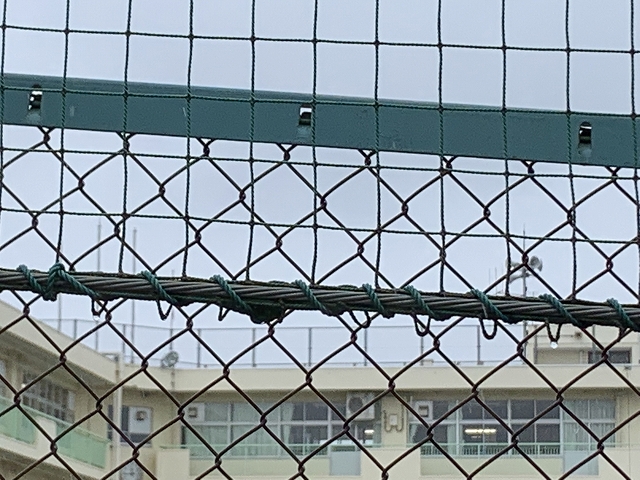
ところが、国立の名門、東京工業大学(近隣には、その、すずかけ台キャンパスがある)では、半旗(弔旗)の掲揚があり、正面入口のところに、半弔旗の掲揚がありました。東京工業大学は、伊勢神宮の神事日(神嘗祭)であることには関心を払わず、羽生田光一文部科学大臣が指示を忠実に守った、あるいは忖度した模様ではないかと、私は見ています。
さて、改めて、半旗と弔旗を調べてみました。以下は、ウキペディア等を参照して記載したものです。その区別がついていなかったので、勉強になりました。
半旗
「弔意を示すため、さおの先から三分の一ほど下に掲げる旗」とされています。
「株式会社平岩 旗事業部」の説明では、以下のように記載されています。→戦争や震災等の犠牲者に対する弔意を表すために「半旗」・「弔旗」といわれる掲揚方法があります。
●震災時に多数の犠牲者が発生した、阪神淡路大震災では半旗が掲げられ、東日本大震災では、その対象が拡大され、毎年の追悼式でも政府が各官庁、学校、企業等に求めていると説明があります。
また、「Weblio辞書」には、以下のように記載されています。→国旗掲揚の作法のうち、主に要人の死に際して弔意の表明として行われる掲揚方法。
●今回の場合は、後者に相当するのでしょうが、「国葬」とは異なります。
弔旗
弔旗に関して、ウキペディアは、以下のように記しています。
旗の竿頭(本来は国家的慶事や国民の祝日の際に祝意を表すため揚げるので、一般に金色の球になっている)を黒布で覆い、その下に旗の長辺長に等しい黒布を結びつけて旗を掲揚する。
●こうしてみると、東京工業大学が掲げていたのが、弔旗に当たります。
また、「国葬」については、別の機会に調べ、記載したいと思います。
#半旗,#弔旗,#内閣自民党合同葬,#国葬,#通達,#国立大学,#教育委員会,#文部科学大臣,#町田市議会議員,#吉田つとむ,
吉田つとむHP 町田市議会議員 吉田つとむのブログ



コメント